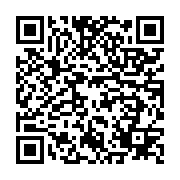お知らせ & コラムNews & Column
-
 2025.4.1
★当院は予約優先制です★
2025.4.1
★当院は予約優先制です★
-
 2025.3.19
★★受診時には資格確認書・保険証をご持参ください★…
2025.3.19
★★受診時には資格確認書・保険証をご持参ください★…
-
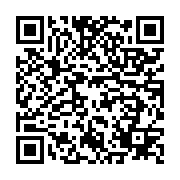 2024.8.2
当院の公式LINEアカウント
2024.8.2
当院の公式LINEアカウント
-
 2024.4.1
横浜市胃がん検診について
2024.4.1
横浜市胃がん検診について
-
 2024.3.22
★重要★発熱、風邪症状のある方へ(完全予約制)
2024.3.22
★重要★発熱、風邪症状のある方へ(完全予約制)
-
 2025.6.19
帯状疱疹ワクチンについて
2025.6.19
帯状疱疹ワクチンについて
-
 2025.1.10
肺炎球菌ワクチンについて
2025.1.10
肺炎球菌ワクチンについて
-
 2025.1.8
インフルエンザワクチンについて
2025.1.8
インフルエンザワクチンについて
-
 2025.1.6
2024−2025年新型コロナワクチンについて(2…
2025.1.6
2024−2025年新型コロナワクチンについて(2…
-
 2024.12.25
子宮頸がんワクチン(シルガード9)
2024.12.25
子宮頸がんワクチン(シルガード9)
-
 2024.12.17
胃もたれでお悩みではありませんか?
2024.12.17
胃もたれでお悩みではありませんか?
-
 2024.12.1
RSウイルスワクチンについて
2024.12.1
RSウイルスワクチンについて
-
 2024.5.28
6月1日から窓口の自己負担額が変わります
2024.5.28
6月1日から窓口の自己負担額が変わります
-
 2024.4.2
7月からの担当医変更のお知らせ
2024.4.2
7月からの担当医変更のお知らせ
-
 2024.3.22
内視鏡検査の予約について
2024.3.22
内視鏡検査の予約について
-
 2024.3.10
ノロウイルスについて
2024.3.10
ノロウイルスについて
-
 2024.3.1
コロナウイルスワクチンについて(3/26終了)
2024.3.1
コロナウイルスワクチンについて(3/26終了)
-
 2024.3.1
短期滞在手術等基本料1の施設基準を取得
2024.3.1
短期滞在手術等基本料1の施設基準を取得
-
 2024.2.14
横浜市健康診査について
2024.2.14
横浜市健康診査について
-
 2024.2.14
脂質異常症とは
2024.2.14
脂質異常症とは