DISEASE病名から探す
胃・大腸の病気Disease
お持ちの症状によって、考えられる疾患は様々です。
病院を受診した際に、どのような症状や状況かお話いただくことで
判断・治療の糸口をみつけ、早期診断、早期治療が可能になります。
胃がん・食道がん・大腸がん
消化管がんには主に、食道がん、胃がん、大腸がんなどがあります。大腸がんと胃がんの死亡者数はがん疾患の中でそれぞれ第2位、第3位(※)を占めており、食道・胃・大腸がんを合わせるとがん全体の死亡者数の約1/3を占めます。(※国立がん研究センター 「2019年
がん登録」より)しかしながら、それらは発見・治療が早期であればあるほど予後が良くなります。
がんは早期でも進行したものでも、時間と共に悪化する病気です。
早期発見できれば内視鏡治療や外科的切除により治癒可能ですが、進行例では骨盤内手術や周術期補助化学(放射線)療法による妊孕性への影響に注意を要します。
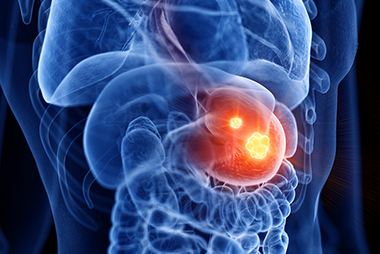
消化管がん(食道がん・胃がん・大腸がん)の症状
いずれも早期の段階では自覚症状はほとんどありません。ある程度進行してくると、食道がんであれば飲み込みにくさや胸の違和感が出現し、胃がんであれば胃の痛み、吐き気、貧血、黒色便などが出現し、大腸がんでは便に血が混じる、便が細くなるなどの症状が出現します
ピロリ菌検査・除菌
ヘリコバクター・ピロリ Helicobacter pylori(ピロリ菌)は、人の胃粘膜に生息し、慢性的な炎症を及ぼし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなど人体に悪影響を及ぼす細菌です。現在の保険診療では、上記の胃潰瘍、十二指腸潰瘍のほか、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡治療後胃、ピロリ菌感染性胃炎(内視鏡検査による確定が必要)に除菌が認められています。日本では年齢とともに感染率は上昇し、10歳台では10%以下に対して、60歳以上では70-80%の感染率といわれています。

アニサキス症
以下の症状がある方は、アニサキス症の疑いが高いです
- みぞおち(上腹部)に激しい痛みを感じる
- 嘔吐・ひどい吐き気を感じる
- お腹に張りを感じる

アニサキスとは寄生虫の一種で、イカやサバをはじめとした魚介類の内臓に寄生しています。
宿主(寄生した先の魚介類)が死亡し鮮度が落ちてしまうと内臓から筋肉のほうへと移動する事がわかっています。
アニサキス症は魚介類の生食が発症の原因であるため、お刺身やお寿司など新鮮な魚介類を食べる場合は注意が必要です。
もし、魚介類を食べた数時間後に上記のような症状を発症された方は、アニサキス症を発症している可能性があります。
アニサキスは人間の体内では生息できず、数日程で胃痛や吐き気などの症状は治まります。しかし、稀に合併症で重症化する可能性がありますので、上記のような症状が診られる方はお早め医療機関までご相談下さい。
必要に応じて内視鏡でアニサキスを摘除することができます。
急性胃炎
急性胃炎とは、原因となることが発生してから短い時間で発症する胃炎のことです。胃炎とは胃粘膜が赤く腫れたりただれたりする状態のことをいいます。
胃の働きには、食べたものを一時的に留めておき、消化したり殺菌したりする働きがあり、このときに必要となるのが胃液です。胃液には胃酸と、消化酵素であるペプシンが含まれていて、胃に入ってきたものを溶かす働きがあります。
胃液にはとても強い酸性の性質があり、胃の壁でも溶かしてしまう力があります。しかし、胃の内側にある粘膜は粘液でおおわれており、この粘液の働きによって胃粘膜は守られています。胃の中は本来、攻撃因子となる胃酸やペプシンなどを含む胃液と、防御因子となる粘液とのバランスが整えられており、胃粘膜が胃酸によって傷つけられることはありません。しかし何らかの理由によってこのバランスが崩れてしまうと、胃粘膜は胃液(胃酸)によって傷つけられ、炎症が起こるとされています。

慢性胃炎
慢性胃炎とは、原因となる特定の病気がないにもかかわらず、胃の粘膜の炎症が長く続いている状態のことをいいます。多くの場合は、ヘリコバクター・ピロリ菌という細菌への感染が原因だと考えられています。
日本人の場合、約70%の人が慢性胃炎であるといわれています。その多くは、胃の粘膜が薄くなってしまう萎縮(いしゅく)性胃炎です。

逆流性食道炎
胃食道逆流症(GERD)とは、胃酸が胃から食道に逆流することで炎症を引き起こす病態のことをいいます。
内視鏡検査で食道粘膜の障害を認めない非びらん性胃食道逆流症(NERD)と食道粘膜の障害を認める逆流性食道炎に分類されます。
報告にもよりますが、逆流性食道炎は4―20%くらいの有病率といわれています。

機能性ディスペプシア
胃がもたれる、腹部が張る、みぞおちが痛い、食後、胃に食べ物が残っている感覚がずっと続く、のような症状が何度も起こる場合、機能性ディスペプシアが疑われます。
機能性ディスペプシアは、胃粘膜に炎症などの器質的異常が見つからないもかかわらず、胃痛やみぞおちの痛み、胃もたれ、早期膨満感(少ししか食べていないのに満腹になる)などの症状が3か月以上何度も起こる病気です。世界中で多くの方が悩まれている病気で、日本では人口の約10人に1人が経験していると言われています。
かつては神経性胃炎と診断され、炎症を抑える治療薬が処方されていましたが、炎症は起きていないため治療効果がありませんでした。しかし、現在では機能性ディスペプシアと診断され、適切な治療を行えるようになりました。

過敏性腸症候群
- 下痢や便秘といった便通異常が長期間続いている
- お手洗いが近く通勤時に不安を感じている
- 排便後スッキリするが直ぐに便意を感じる
- 緊張すると直ぐにお腹を下してしまう
- 休日は何ともないのに平日になると調子が悪くなる

過敏性腸症候群とは、長期間続く腹痛やお腹の不快感、便秘や下痢といった便通異常が特徴である病気です。
精神的なストレスや不安を長い間感じ続ける事で副交感神経系に異常が発症します。
便を体外に出そうとする腸管のぜん動運動が不規則となり、それが原因で便秘や下痢を引き起こしたり、腸管が過敏状態となってしまい、少しの刺激で腹痛を感じたりします。
ぜん動運動とは、腸管内容を腸が伸びたり、縮んだりをくり返して腸内を移動させ、体外へ排出する動きです。
また近年では、過敏性腸症候群を発症する方は増加傾向にあり、過敏性腸症候群は約10人に1人の割合で発症しているとも言われています。それほど過敏性腸症候群は身近な疾患なのです。
過敏性腸症候群が発症すると、下痢や便秘だけでなく腹痛、お腹の張りなど様々な症状を引き起こします。
これらの症状は長期間続く事が多いので、過敏性腸症候群は日常生活にも大きく関わってきます。
便秘
- 数日間、排便していない
- 排便に時間が掛かる、排便後に便が残っている感じがする
- 力まないと便が出ない、便が硬い
- お腹が張り苦しい、腹痛が続く
- 肌荒れが起こるようになった

便秘とは排便されず腹痛などの症状を引き起こす疾患であります。
排便習慣や排便回数には個人差があります。必ずしも毎日排便をしないからといって、便秘と診断される事はありません。
数日から1週間に1度の排便であってたとしても、腹部症状を感じる事がなく、特に困っていない場合には治療が不要な場合があります。
一方で、毎日排便をしていても排便後にスッキリしない、お腹の張りや腹痛を感じる際には治療を行う必要があります。
便秘の警告徴候(大腸カメラ検査を受けた方が良い方)
- 最近排便異常を発症した方
- 急に体重が減少した方
- 大腸がんの家族歴がある方
- 血便症状が発症している方
- 40歳以上の方
これらの項目に該当する場合は大腸がんなどのリスクが高くなるため、一度ご相談下さい。
下痢
- 水状、泥状の下痢が長期間続く
- トイレから離れられない程頻繁に下痢が続く
- 下痢に血が混じる

便中に含まれる水分量が増加し、便としての形状を保てなくなり液状または泥状のまま排出されることを下痢と言います。
下痢の発症原因も様々あります。
下痢は体の不調を示す大切な兆候であり軽視できない場合もあります。
下痢が続くと脱水症状を引き起こしたり、電解質やタンパク質など人が生きていく上で必要となる栄養素も失ってしまいます。
便潜血・血便
- 排便後に拭いた紙に血が付いている
- 排便後に便器内が真っ赤になっていた
- 黒い便がでた
- 便潜血検査が陽性だった

便潜血・血便の症状がある方は、大腸カメラ検査受診を推奨します
痔以外では直腸がんでも鮮血便を認める時もあり、鮮血便を発症している場合は詳細な問診や直腸診で判断し、内視鏡検査(大腸カメラ検査)で大腸の精密検査を行う必要があります。
血便がでたら直ぐに受診しましょう
血便は消化管内で異常が発症しているサインです。ご自身の身体に発症している些細な変化を都合の良い解釈をしないで、一度ご相談ください。
いつ血便が出たのか、血便は毎日出ているのか、血便以外で発症している症状はあるのかなど問診・精密検査を行い、血便が発症している原因を特定していきます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍と十二指腸潰瘍とは、分泌された胃液の刺激によって胃や十二指腸の組織が消失・欠損してしまう疾患です。痛みや出血(吐血・下血)、穿孔(孔が空いてしまう)などの合併症を引き起こす恐れがあります。
昔は再発を繰り返すことから、完治が極めて難しい疾患だと思われてきました。手術が行われることも多かったのですが、近年では新薬が開発されたり研究が進んで原因が解明されたりするようになったため、内服治療だけでほぼ完治できる疾患となりました。

十二指腸炎・びらん
十二指腸炎・びらんとは十二指腸の粘膜がただれて傷ついた状態です。
軽症ではあまり症状はなく、胃カメラ(内視鏡)を行ってたまたま見つかることもありますが、程度が強くなると、みぞおちや背中の痛み・吐き気・不快感などの症状が現れることがあります。
またひどくなると出血を伴ったり、痛みや吐き気で食事がとれなくなったりすることもあるため、症状が気になる時には胃カメラ(内視鏡)を行い他の病気の有無も含め状態をチェックすることが重要です。

潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎(UC)は、大腸の内側(粘膜)に慢性的な炎症を引き起こす自己免疫疾患の一種で、日本でも患者数が増加傾向にあります。主な症状として、下痢・血便・腹痛・発熱が挙げられ、進行すると貧血や体重減少を伴うこともあります。寛解期(症状が落ち着いている時期)と活動期(症状が強くなる時期)を繰り返すことが特徴です。

原因
潰瘍性大腸炎の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因・免疫系の異常・腸内細菌のバランスの乱れ・環境因子などが関与していると考えられています。家族内発症が見られることから、遺伝的素因がある人が、ストレス・食生活の変化・感染症などを契機に発症する可能性が示唆されています。
症状
腹痛、下痢、血便を起こすことが多く、血便では粘血便という粘液が混じったものもよく起こります。理由のない体重減少や貧血で気付く場合もあります。感染症の細菌性赤痢やサルモネラ腸炎などでも同様の症状を起こすこともありますし、同じく難病指定されたクローン病と寛解期と再燃期を繰り返すといった特徴も共通しています。それぞれ適切な治療を早急に受けることが重要な疾患ですし、特にクローン病との鑑別は重要です。疑わしい症状がある場合には必ず消化器内科を受診して大腸カメラ検査を受けるなど、正確な診断による適切な治療を受けてください。特に寛解期で治ったと勘違いして治療を中断してしまうと悪化して症状を再び生じる再燃を起こすため注意してください。
診断と検査
潰瘍性大腸炎は、症状・血液検査・便検査・内視鏡検査・組織検査(生検)総合的に評価し診断します。特に内視鏡検査は、潰瘍性大腸炎の確定診断に不可欠です。
早期発見・正確な診断が重要となり、 症状が軽度でも、放置すると悪化することがあるため、血便や下痢が続く場合は早めの受診をおすすめします。
- 血液検査:炎症の程度(CRPや白血球数)、貧血の有無を確認
- 便検査:感染性腸炎との鑑別
- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ):粘膜のびらん・潰瘍の範囲を直接観察
- 組織検査(生検):内視鏡検査中に採取した粘膜を顕微鏡で分析し、確定診断
最新の治療法
潰瘍性大腸炎の治療は、症状の軽減(寛解導入)と、再発を防ぐ(寛解維持)ことが目的です。病状の重症度に応じて、適切な治療法を選択します。
新しい治療法の選択肢が増え、より個々の病状に合わせた治療が可能になっています。
5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤(サラゾピリン®、ペンタサ®、アサコール®)
- ・軽症~中等症の第一選択薬
- ・腸粘膜の炎症を抑える効果があり、内服薬や注腸(肛門からの投与)が可能
経口ステロイド(プレドニン®、ブデソニド®)
- ・中等症~重症の急性増悪期に使用
- ・長期使用は副作用(骨粗鬆症、高血糖、感染症リスク)に注意
免疫調節薬(アザチオプリン、6-MP)
- ・ステロイドの減量・寛解維持に有効
- ・特にステロイド依存性の患者さんに使用
生物学的製剤(抗TNFα抗体・JAK阻害剤・IL-23阻害剤)
- ・抗TNFα抗体(インフリキシマブ・アダリムマブ)
- ・インテグリン阻害薬(ベドリズマブ)
- ・JAK阻害薬(ウパダシチニブ・トファシチニブ)
- ・IL-23阻害薬(リサンキズマブ・グセルクマブ)
近年、潰瘍性大腸炎に対して分子標的治療が使用されております。
栄養療法・生活習慣の改善
- バランスの取れた食事(低脂肪・低残渣食が推奨されることも)
- ストレス管理(ストレスが悪化因子となる可能性あり)
- 禁煙
診療
当院では、最新の診療ガイドラインに基づき、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しています。
「血便や下痢が続いている」「治療中だが症状が改善しない」など、不安な症状がある方は、ぜひご相談ください。
大腸ポリープ切除
大腸ポリープの多くは腺腫ですが、これは放置していると一部ががん化する可能性がある前がん病変です。当院では、大腸ポリープの日帰り切除手術を行っています。また、大腸カメラ検査中に発見した大腸ポリープは高度な画像処理などを用いて精緻に観察して切除が必要と判断された場合には、その場で日帰り手術による切除も可能です。
大腸がんは進行が比較的ゆっくりしていますが、進行がんになってしまうとリンパ節や他臓器への転移を起こして大変な治療が必要になりますし、命の危険につながることもあります。現在、がんによる死亡原因としても近年、上位を占めています。ただし、大腸がんは早期に発見することで日常や仕事に影響しない楽な治療でほとんどの場合は完治可能ですし、ポリープの段階で切除することで予防もできます。

安全性の高い日帰りポリープ切除
当院では、特殊な光や画像処理によって微小な病変や変化を発見可能な高性能の内視鏡システムを導入しています。また、検査は2万例以上の内視鏡検査や治療を経験してきた院長が行っており、高度な技術を用いて丁寧に検査、処置、治療しています。また、発見した大腸ポリープは、サイズ、形、構造などを詳細に観察して、切除の必要性や適切な切除手法を判断しています。大腸ポリープの切除は日帰り手術が行われるほど侵襲が少ないという特徴がありますが、当院ではより安全性を高めた切除を行っています。 なお、まれですが、ポリープの大きさや形状などによっては日帰り手術による切除が適切ではないケースも存在します。出血する可能性が高い、がんの疑いがある、きれいに取り切れない可能性がある、サイズが大きい、数が多い、深い場所に食い込んでいるなどの場合には、地域連携している高度医療機関をご紹介してスムーズな治療を受けていただけるようにしています。
クローン病
クローン病は、消化管全体、とくに小腸や大腸に慢性的な炎症が起こる疾患です。炎症により腸粘膜にびらんや潰瘍が生じます。原因は明確ではありませんが、自己免疫の異常によってTNF-αという物質が過剰に産生され、炎症に関与していると考えられています。
炎症の部位により、小腸型・大腸型・小腸大腸型に分類され、症状や治療法も異なります。完治する治療法はありませんが、適切な治療により炎症をコントロールし、発症前と変わらない生活を送ることが可能です。
一方、炎症が続くと重症化や合併症、大腸がんのリスクが高まります。潰瘍性大腸炎と似ていますが、クローン病は炎症が深部まで及び、口から肛門まで病変が生じる点が特徴です。栄養不良を伴うこともあり、その場合は栄養療法を行います。適切な治療のためには正確な鑑別診断が重要です。

大腸憩室症
憩室(けいしつ)とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に突き出した状態を指します。慢性的な便秘などによって腸の内側の圧力が高まると、腸壁の弱い部分が押し出されるようにして形成されます。
また、赤身肉のとり過ぎや食物繊維不足といった食生活の乱れをはじめ、肥満、運動不足、遺伝的要因、喫煙、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の使用なども、発生に関与すると考えられています。
一度できた憩室は自然に消えることはなく、年齢とともに数が増えていく傾向があります。

腸閉塞
腸閉塞は別名「イレウス」と呼ばれており、様々な原因で腸がふさがってしまい、食べ物や飲み物、ガスなどが通過しないようになってしまう病気です。
腸閉塞は急激な腹痛を伴う病気の中で、虫垂炎の次に発症件数が多いといわれ、大人だけでなく、生まれたばかりの子供にも発症する可能性があります。

腹膜炎
腸を包んでいる腹膜が何らかの原因によって炎症を起こす病気です。原因はさまざまですが、多くの場合、腹腔内臓器の炎症、あるいは胃や十二指腸、大腸などの消化管の壁に穴があき、内容物が外にもれ出て広がることで起こります。
急な激しい痛みに襲われる急性腹膜炎と、痛みが出たり消えたりをくり返す慢性腹膜炎があり、約95%が急性腹膜炎です。緊急手術が必要になるケースも少なくなく、放っておくと命にかかわることもあります。

胆石症
胆石症とは胆のうや胆管内にコレステロールやビリルビンなどが固まって結石となる事で、痛みなど様々な症状を引き起こす病気です。結石とは胆汁中に含まれている成分が凝集して結晶化したものを言います。結石が発症している部位で、「胆のう結石」、「総胆管結石」、「肝内胆管結石」などがあり、胆のうの中で発症する結石の事を胆石と呼びます。
肝臓は内臓の中で一番大きな臓器で、この肝臓で1日に約500~800mlの胆汁が作られます。この胆汁は胆管を通り膵管と合流し、膵臓から排出される膵液と共に十二指腸へと分泌され、脂肪や炭水化物の消化を助けています。
胆のうは食べ物の消化吸収を助ける胆汁を溜める役割を持ちます。

胆のう炎
胆のう炎には急性胆のう炎と慢性胆のう炎があります。急性胆のう炎は、結石により胆のう管が閉塞してしまうことに続いて、胆のう壁の粘膜が炎症をおこすものですが、細菌感染が加わると重症化することもある危険な疾患です。慢性胆のう炎は、繰り返される炎症によって胆のう壁が厚くなり、胆のう自身は収縮していきます。

胆管炎
肝臓から十二指腸まで伸びる「胆管」に炎症が起こる病気です。胆管は、肝臓でつくられて胆嚢で一時貯留・濃縮された胆汁の通り道です。何らかの原因で胆管が閉塞し、胆汁がスムーズに流れずにうっ滞が生じると、胆汁中の細菌などに感染を起こし、胆管に炎症が発生します。死亡率は2.7~10%とされ、重症例は化膿性胆管炎といわれ、速やかな診断・治療が必要です。

生活習慣病disease
糖尿病
今や日本人にとって“国民病”ともいえる糖尿病。40歳以上では約3人に1人が糖尿病(または糖尿病予備軍)とされ、「糖尿病が強く疑われる人」「糖尿病である可能性を否定できない人」を含めるとその数は2250万人以上にのぼります。
当院では糖尿病の疑いがある方をはじめ、治療を継続しながらも改善がみられない方などを幅広く診療しています。それぞれの患者さんに適した検査や治療をご提供することができますので、ぜひご相談ください。

高血圧
血圧が高い状態が続く事で血管の壁に圧力が掛り、その結果、血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化へとつながります。
高血圧の原因は特定されていませんが、遺伝的要因と食生活(塩分の高い食事)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、または運動不足や精神的なストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。

脂質異常症
血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が多い為に引き起こされる疾患です。
これらの余分な脂質は、動脈の壁にくっついて血管を硬く狭くしていずれ動脈硬化を引き起こします。
コレステロールには善玉コレステロール(HDL)と悪玉コレステロール(LDL)があり、善玉コレステロールは細胞内や血管内の余分な脂質を肝臓に戻す働きがある為、悪玉コレステロールを減らすことに役立っています。
高脂血症の主な原因は食生活(カロリー過多)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、運動不足、遺伝などが考えられます。

高尿酸血症(痛風)
近年、食生活の欧米化や生活習慣の変化で高尿酸血症・痛風のかたが日本でも増加しています。
高尿酸血症の定義は血清尿酸値が7.0 mg/dlを超えるものと定義されています。
高尿酸血症の状態が続くと、関節内に尿酸の結晶が生じるため関節炎を起こします。
ある日、足の親指の付け根などの関節が赤く腫れて強く痛みます。これを痛風発作といいます。足の親指の付け根以外にも、他の関節に発作が起こることもあります。

不眠症
睡眠は個人差が大きく、少ない時間でも平気な人もいますし、7時間以上眠っても熟睡感が得られない人もいます。
このように長時間寝ていても、本人が不眠を自覚する場合は不眠症と判断されます。
不眠症には、「寝付きが悪い(入眠障害)」、「寝た気がしない(熟眠障害)」、「朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)」、「ちょくちょく目が覚める(中途覚醒)」などがあります。
不眠の原因を調べ、その治療を行うことでほとんどの症状を軽快させることができます。
睡眠は大切なものですので、お悩みの方はご相談ください。

